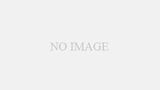こんにちは。税理士の筒井です。
今日は川崎市宮前区の平小学校に租税教室の講師としてお呼ばれしたので行ってきました。
今回は、小学校6年生の1時間目でした。授業中は、税金に関するクイズなど織り交ぜながら進行し、生徒さんはたくさん発言してくれました。
事前に、生徒さんから税金に関する質問を文書でいただいたので、回答させていただきました。
質問内容が面白いと感じたので、今日のブログで12個の質問をご紹介したいと思います。
目次
質問1 :1人当たりの一年間の税金はいくらぐらいですか?
日本の個人の所得税は、累進課税と言って、収入(所得)によって税率が変わりますので、個人によって税金の金額がそれぞれ違います。
なので、令和4年国税庁民間給与実態調査統計から、日本の平均年収458万円と言うデータがあったので、それをもとに計算をしてみました。
458万円はボーナスも含んだ金額のようですが、計算は月間給与38万円と言う前提で簡単に計算しました。
複雑な計算はしていませんので大体の金額です。
所得税11万2400円、住民税、20万9900円、合計322,300円、社会保険約年間64万円。
458万円のうち100万円近く支払うわけですね。
質問2:なぜ、消費税は10%なんですか?
国が歳入・歳出などの統計値や予算などから決めたものでしょうが、なぜ10%なのかは正直分かりません。
消費税の歴史は、平成元年の消費導入時3%、その後5%、8%、10%と増税して現在に至ります。
社会保障など、国の予算に使うため、国会議員が国会で話し合った結果ですね。国会議員を決めるのは、国民一人一人なので、不満があるのであれば、せめてできることとすればしっかり投票に行かなければいけませんよね…。
完全に私個人の価値観が入っています。人によってさまざまな考え方があります。
質問3:税金はいつからあるんですか?
現在のわが国の税制の基礎ができたのは、戦後の昭和25年にアメリカをお手本にしてできたようです。(詳しく知りたい方はシャウプ勧告と調べてみてください。)
税金の仕組みが初めてできたのは定かでないが、国税庁サイトで紹介している日本の税の歴史としては、飛鳥時代からすでにあったようです。
租庸調という制度で、私も昔この言葉は歴史の教科書で習った気がします。
質問4:余った税金の行方が知りたいです
国の予算はその年度で全部使い切ることが原則なので基本は余らないようです。(単年度主義)
もし余ってしまったら、予算は繰り越され、次年度の国の予算に当てられます。
(参考 NHKサイトより 予算の繰り越し 過去最大30兆円余に 理由は?|サクサク経済Q&A|NHK)
基本的に税金は余る事はなく、国家の予算に合わせて国家のために使われている。はず。。。
質問5:なぜ、増税したんですか?
国の運営のための資金が必要になり、現在よりも国民から徴収する額を増やして、その予算に当てていると思います。
そのほか、急激な景気の動きを抑える。などたくさんの複雑な事情がありますね。国も会社の経営と同じように将来の収入や支出を予測して動いているわけで、必要な額を集めなければならない場合は増税して資金を確保するわけです。
質問6:国と地方税に分かれているのはなぜですか?
国の運営は、国自体が行うものと、地方公共団体(都道府県市区町村)が行うものの2つがあります。
国税は国の財源になります。
地方税は、地方公共団体の財源になります。
教育、福祉、ゴミ処理など、生活に結びついた公共サービスは地方公共団体によって提供されているので、公共サービスの費用を住民で共同して負担し合うと言う考えから設けられた税金が地方税。
したがって、国と地方それぞれ別々に納付することになっています。(引用 総務省サイト)
質問7:なぜ、税金はあるんですか?
国民が安心して暮らせる社会づくりのために使われます。
国を動かすためには莫大なお金がかかるので税金が必要になってくるわけです。
質問8:税金の種類で一番集まるのは何税ですか?
消費税が令和6年現在トップ。金額第1位です。
消費税、34.9%、個人所得税26.7%、法人所得税24.4% 資産税等14%(令和6年)
消費税は、令和4年までは第2位で、第1位はいつも個人所得税だったのですが、令和5年から1位に踊り出てきました。
消費税は、免税だった個人事業主がインボイスの改正により課税事業者にならざるを得ないことなど、税率の変更は無いものの、実質的な俗にいうステルス増税(皆が気づきにくい増税)があったことなどが大きく影響しているのではないでしょうか。
ちなみに、日本の一年あたりの税収はどのぐらいあるかというと、約69兆円(令和6年予算)です。
質問9:税金のメリットは?
基本的には誰しも、税金は好き好んで払いたくないものですが、税金を払うメリットは当然あります。
国の公共施設や公共サービスが増えればにより住みやすい国となる。医療費がタダ、もしくはほとんどかからないなど、医療が充実した福祉国家になれば生きやすい。
防衛費などに税金を投入することで国を守ることができる。
貧富の差をなくす。余裕のある人から多めにもらい、生活が厳しい人からは少なくもらう。
などでしょうか。
質問10:大谷翔平選手の税金はいくらぐらいですか?
おもしろい質問だと思いました。
大谷選手は海外に住んでいるようですので、非居住者となればアメリカで獲得した収入は日本の税金がかからないということになりますが、私は野球にそんなに詳しくないですし、詳細は不明なので、もし、日本の税金がかけられたと仮定すると、ということで計算してみました。
ネットニュース記事で年俸を確認してみました。
大谷選手の2024年シーズンの年俸は200万ドル(約2億9000万円/1ドル145円換算)(某ニュースサイト)の場合、所得税の最高税率45%+住民税10%=55%なので、およそ1億5千950万円となります。
ただし、上記は、広告収入など、球団からの収入等以外は全然考慮していませんので、実際はもっと桁違いにすごい金額だと思います。
しかも、実際は、10年で7億ドル(約1,015億円)受け取る契約のため、年間100億円が収入になるべきところを、アメリカの贅沢税というものが球団側にかかってしまうという大人の事情から、年間2億9000万円の受け取りに留めているとのことです。
日本の税金がかけられたら、超過累進税率の最高税率45%+住民税10%=55%、つまり、55億円が毎年の納税額になります!!凄いですね。
質問11:税金がない国はあるんですか?
税金が全くない国があるかは、調べきれず私には正確には回答できません。すみません…
ドバイが有名なアラブ首長国連邦(UAE)は所得税がないようです。石油が取れるから取る必要がないのでしょうか。
質問12:税金の使い道は誰がきめているんですか?
国民により選挙で選出された国会議員が国会議事堂で話し合って決めています。
さいごに
今回は、租税教室で、特に子供たちからの質問について個人的な見解を含めて書いてみました。
税金は国を動かす重要な要素で、政治に常に利用されてます。租税政策と言ったりします。
租税政策の例を1つあげますと、法人税の交際費は中小企業は年間800万円まで損金(経費のこと。経費は税金を減らす効果があります。)になりますが、昔400万円、600万円が限度の時期もありました。
時の首相が、経済を活性化させるために、企業の交際費の損金となる限度額を800万円まで引き上げました。
そうすると、
企業は積極的に接待交際費を増やす➡飲食店など、お店の売り上げが上がる➡従業員さんの給料も増える➡経済が活性化する
このように考えられたからです。
現在も中小企業は交際費年間800万円までは損金になります。(正確には800万円×当期の事業年度の月数/12)
※大企業は800万円という枠はなく、原則として交際費は損金になりませんが、接待飲食費の50%だけは損金として認めてくれます。資本金100億円超の大企業は一切損金に認められません。
このように政治的に利用されますので、税金を勉強していると、政治のニュースが面白くなる時があります。(たまに)
今回は以上です。
最後までお読みいただきありがとうございました。
税理士/元資格の大原法人税法非常勤講師(2019年~2024年の5年間)
1982年生まれ
平成31年3月 税理士登録
2021年3月に独立 筒井一成税理士事務所を川崎市宮前区にて開業
2024年3月 事務所を世田谷区等々力に移転
現在世田谷区等々力を拠点として活動中。主に法人の顧問や相続のご相談をお受けしています。
ブログでは役に立つ税金の情報などを中心に発信していきます。
詳しいプロフィールはこちら
免責事項
本サイトのブログ内容は、投稿時点での税法その他の法令に基づき記載しています。
掲載記事に関する情報により被ったいかなる損害に関して、弊所は一切の責任を負わないものとします。
本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家にご相談の上行ってください。