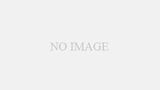こんにちは、税理士の筒井一成です。
令和7年度(2025年度)の税制改正は、企業経営と家庭の暮らしの両面に大きな影響を与える重要な内容が多く含まれています。
今回は経営者にとって押さえておきたい改正点を、わかりやすくご紹介します。
目次
1. 法人税の軽減税率の見直し
- 資本金1億円以下の中小企業に適用されている800万円以下部分への法人税軽減税率(15%)は令和9年3月末まで延長されました。
- ただし、年間所得が10億円を超える企業は15%→17%に引き上げられます。
- グループ通算制度を使う法人は軽減税率の適用対象外となる点にも注意が必要です。
2. 防衛特別法人税の創設
- 法人税額に対して4%の追加課税が予定されています。
- 法人税額が500万円以下の場合は非課税。
- 適用は令和8年4月以降の開始事業年度から。
企業にとっては、実質的な法人税負担増となるため、事前に資金繰りや納税シミュレーションが必要です。
3. 個人所得税の控除拡大
- 基礎控除が48万円から58万円に増額されます。
- 給与所得控除も一律10万円増額され、給与所得者の手取りが増える効果があります。
この改正は、役員・従業員の家計支援にもつながり、結果として企業の人材定着や満足度向上にも寄与するでしょう。
4. 賃上げ促進税制の拡充
- 一定割合以上の賃上げ(例:3%以上)を行った企業に対し、**法人税の税額控除(最大40%)**が適用されます。
- 研修費の増額などを組み合わせることで控除率が拡大される仕組みです。
5. 特定親族特別控除の創設(大学生を扶養する親の支援)
これまで、19歳以上23歳未満の子がアルバイトなどで年収103万円を超えると親の扶養控除(63万円)を受けられませんでした。
この「103万円の壁」を緩和するために**「特定親族特別控除」**が創設されます。
- 年収150万円以下の子:従来どおり63万円の控除対象。
- 年収150~188万円:控除額は段階的に減少。
- 年収188万円超:控除の対象外。
これにより、大学生の子どもが一定の収入を得ても、親の税負担が急増しない仕組みが整います。
6. 子育て世帯向け税制支援の拡充
子育て支援の一環として、以下のような税制措置も導入・拡充されます。
● 生命保険料控除の上限引き上げ
- 23歳未満の子を扶養する親について、生命保険料控除の限度額が4万円→6万円に(令和8年から適用)。
● 住宅ローン控除の借入限度額を上乗せ
- 認定住宅を購入する子育て世帯に対し、**借入限度額が従来よりも上乗せ(最大5,000万円)**されます。
● 子育て対応リフォームに対する所得税控除
- 一定のリフォーム工事(例:バリアフリーや間取り変更等)に対して、工事費の10%が所得税額から控除される特例が新設。
これらの制度は、子育てと仕事の両立を後押しする強力な支援策として期待されています。
7. 電子帳簿保存制度の見直し
- 一定の電子帳簿が「優良な電子帳簿」として認められる要件を見直し。
- 青色申告特別控除(65万円)を受ける条件として、新たに“特定電子計算機処理システム”の使用が認められます。
- 訂正・削除履歴の保存要件の緩和、検索機能の簡素化など、事務負担の軽減も図られます。
- 中小企業や個人事業主にとって、電子帳簿保存のハードルが下がり、デジタル化への移行がしやすくなりました。
まとめ
令和7年度の税制改正では、以下のテーマが重視されています:
- 中小企業への税率支援の再整理
- 賃上げ・教育投資への強力な後押し
- 所得税控除の拡大による家計支援
- 子育て世帯・大学生を持つ家庭への新たな税控除の創設
私は税理士として、これらの制度を経営にどう活かすかを共に考え、実行までサポートします。
制度は知るだけでなく、「使いこなしてこそ意味がある」と考えています。
【参考・引用元】
- 財務省『令和7年度税制改正のポイント』https://www.mof.go.jp/tax_policy/publication/brochure/zeisei2025_pdf/zeisei25_all.pdf
- 国税庁『令和7年度税制改正に関する資料』https://www.nta.go.jp/publication/pamph/zeisei/2025/index.htm
税理士/元資格の大原法人税法非常勤講師(2019年~2024年の5年間)
1982年生まれ
平成31年3月 税理士登録
2021年3月に独立 筒井一成税理士事務所を川崎市宮前区にて開業
2024年3月 事務所を世田谷区等々力に移転
現在世田谷区等々力を拠点として活動中。主に法人の顧問や相続のご相談をお受けしています。
ブログでは役に立つ税金の情報などを中心に発信していきます。
詳しいプロフィールはこちら
免責事項
本サイトのブログ内容は、投稿時点での税法その他の法令に基づき記載しています。
掲載記事に関する情報により被ったいかなる損害に関して、弊所は一切の責任を負わないものとします。
本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家にご相談の上行ってください。