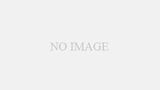親族が亡くなると遺族は短期間で多くの手続きをこなさなければなりません。特に銀行口座の凍結解除は「書類がそろわず払戻しが遅れる」「相続人間でトラブルになる」などの相談が最も多い分野です。
本記事では①全体スケジュールと②銀行手続き4ステップをまとめました。
相続発生後の主な期限
| 期限の目安 | 手続き | ポイント |
|---|---|---|
| 7日以内 | 死亡届提出 | 戸籍法に基づき市区町村へ提出。届出後、銀行は口座を凍結。 |
| 3か月以内 | 相続放棄・限定承認 | 家庭裁判所へ申述。負債が多い場合は要検討。 |
| 4か月以内 | 準確定申告 | 被相続人の1/1~死亡日までの所得税申告。 |
| 10か月以内 | 相続税申告・納付 | 現金一括納付が原則。延納・物納は要件あり。 |
銀行(預貯金)手続きは4ステップ
- 手続き申出
相続人代表者が支店窓口や電話で「相続発生」を連絡。銀行から相続手続依頼書セットを受け取ります。 - 必要書類をそろえる
- 公正証書遺言または検認済遺言書(遺言がある場合)
- 遺産分割協議書+相続人全員の実印・印鑑証明(遺言がない場合)
- 被相続人の除籍謄本(出生~死亡)と各相続人の戸籍謄本
書類不備が最も多いので早めに戸籍を一括請求しましょう。
- 書類提出・銀行審査
相続届や代表相続人届に全員が署名・実印押印。審査は2~4週間が目安ですが、記載不備や相続人が海外在住の場合はさらに延びます。 - 払戻し・解約
審査完了後、口座解約+相続人の指定口座へ振込が一括で行われます。定期預金・外貨預金・貸金庫・投資信託も同時に手続き。
最大150万円まで単独で引き出せる「預貯金の仮払い制度」
2019年の民法改正で創設された制度により、各相続人は
残高 × 1/3 × 法定相続分(上限150万円)
の範囲で単独払戻しを請求できます。
例:残高900万円・相続人2人(各1/2)→150万円まで即日引き出し可。
葬儀費用など急な支払いに便利ですが、必要書類(戸籍・印鑑証明等)は通常手続きと同じなので注意してください。
トラブルを防ぐ3つの注意点
- ATMでの先引き出しは避ける
他の相続人から「特別受益」とみなされる恐れがあります。 - 遺言書の有無を必ず確認
検認前の自筆遺言はすぐに使えないため、家庭裁判所で検認手続きが必要です。 - 期限管理
相続税の申告・納付(10か月)は銀行手続き完了の有無に関係なく到来します。
まとめ
– 銀行口座は死亡が伝わった瞬間に凍結。
– 必要書類は戸籍・遺言・遺産分割協議書が三本柱。
– 葬儀費用など急ぎの支出には仮払い制度(上限150万円)を活用。
– 相続税申告など法定期限は延びないので、手続きは並行して進めましょう。
わからない点があれば、早めに税理士や司法書士へご相談ください。
税理士/元資格の大原法人税法非常勤講師(2019年~2024年の5年間)
1982年生まれ
平成31年3月 税理士登録
2021年3月に独立 筒井一成税理士事務所を川崎市宮前区にて開業
2024年3月 事務所を世田谷区等々力に移転
現在世田谷区等々力を拠点として活動中。主に法人の顧問や相続のご相談をお受けしています。
ブログでは役に立つ税金の情報などを中心に発信していきます。
詳しいプロフィールはこちら
免責事項
本サイトのブログ内容は、投稿時点での税法その他の法令に基づき記載しています。
掲載記事に関する情報により被ったいかなる損害に関して、弊所は一切の責任を負わないものとします。
本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家にご相談の上行ってください。