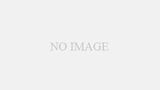民法は法律婚の配偶者+血族(子→直系尊属→兄弟姉妹)を法定相続人と定めており、事実婚のパートナーや愛人には原則として相続権がありません。そのままでは一円も遺産を受け取れないため、遺言・生前贈与・生命保険などの対策が欠かせません。
法定相続人になれない理由
民法887条~890条は「届出婚の配偶者」のみを保護します。内縁の妻・夫や愛人は血族にも配偶者にも該当しないため、相続開始時点では相続権はゼロとなります。
パートナーに財産を残す3つのルート
- 遺言(遺贈):遺言書で「全財産を○○に遺贈」と明記すれば取得可能。
- 生前贈与:年間110万円まで非課税。超過分は贈与税が課税。
- 生命保険:保険金は受取人固有財産として直接渡る(みなし相続財産)。
遺留分とは?──最低限の取り分を保証する制度
遺留分は兄弟姉妹を除く相続人(配偶者・子・直系尊属)に認められた「最低限の取り分」です。被相続人が遺言や贈与で財産を自由に分配しても、遺留分を侵害された相続人は遺留分侵害額請求(2019年改正で金銭債権化)により取り返すことができます。
遺留分の割合(総遺産に対する全体分)
- 配偶者または子がいる場合 …… 1/2
- 配偶者のみ、または直系尊属のみの場合 …… 1/3
- 兄弟姉妹には遺留分なし
各遺留分権利者は、この全体分を法定相続分で按分した額を請求できます。
例: 1億円の遺産をすべて愛人に遺贈したケースで、配偶者と子1人がいる場合
- 遺留分総額=1億円×1/2=5,000万円
- 配偶者の請求額=5,000万円×1/2=2,500万円
- 子の請求額=同上2,500万円
愛人は遺留分請求に応じて合計5,000万円を金銭で支払う義務が生じるため、実際に残せる額は最大5,000万円に目減りします。
相続税の「2割加算」も要注意
被相続人の「配偶者・一親等の血族」以外が遺贈や相続で財産を取得すると、相続税が自動的に20%上乗せされます。パートナーが多額の相続税を納められるか事前に試算しましょう。
遺言を作成する際の実務チェック
- 公正証書遺言で形式不備リスクを回避。自筆の場合は法務局保管制度も活用。
- 遺留分を侵害する内容なら、現金や保険で遺留分請求資金を確保する案も検討。
- パートナー側の納税資金:取得額×120%で資金を用意しておくと安全。
まとめ
事実婚・愛人に遺産を残すには
①遺言
②生前贈与
③生命保険
の三本柱が基本です。ただし相続人には遺留分、受遺者には相続税2割加算が立ちはだかるため、<残せる額>と<納税資金>を試算した上で遺言内容を設計しましょう。
税理士としては、遺留分試算と相続税シミュレーションを早い段階で行い、紛争と納税トラブルを未然に防ぐことが重要です。
税理士/元資格の大原法人税法非常勤講師(2019年~2024年の5年間)
1982年生まれ
平成31年3月 税理士登録
2021年3月に独立 筒井一成税理士事務所を川崎市宮前区にて開業
2024年3月 事務所を世田谷区等々力に移転
現在世田谷区等々力を拠点として活動中。主に法人の顧問や相続のご相談をお受けしています。
ブログでは役に立つ税金の情報などを中心に発信していきます。
詳しいプロフィールはこちら
免責事項
本サイトのブログ内容は、投稿時点での税法その他の法令に基づき記載しています。
掲載記事に関する情報により被ったいかなる損害に関して、弊所は一切の責任を負わないものとします。
本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家にご相談の上行ってください。