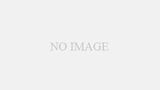こんにちは。税理士の筒井です。
今回は、役員に支給する賞与で社会保険料の節約についてお話ししていきたいと思います。
目次
役員報酬or役員賞与 どっちが安い?
役員報酬の場合、月額報酬に対して、社会保険料が決まり、上限はありますが、健康保険は月額139万円、厚生年金は月額65万円が上限となってます。
社会保険料率とインターネットで検索すると、健康保険厚生年金保険の保険料額表を見ることができます。
役員報酬が月100万円の場合、保険料額表に当てはめると下記のようになります。
通常の役員報酬の社会保険料
役員報酬100万円(年収1200万円)の場合、健康保険・介護保険11万3,484円/2=5万6,742円(会社との折半で、2分の1が従業員や役員の負担額となる。)+厚生年金保険11万8,950円/2=5万9,475円となり、年間139万4,604円の負担になります。
役員賞与にした場合の社会保険料
ところが、役員報酬100万円(年収1200万円)を賞与として支給した場合、健康保険の上限が年間、累積573万円、厚生年金が年間累積150万円が上限になるので、健康保険、介護保険は573万円× 11.58%(令和6年3月分現在東京都の料率)/2 +厚生年金= 150万円× 18.3%/2=46万9,017円です。
139万4,604円− 46万9,017円の差額92万5,587円が保険料の節約額となります。
年間573万円を超える賞与を支給した場合はそれ以上保険料が上がらないことを利用した社会保険料を下げる手法のカラクリです。
社会保険料を安くするスキームを使うメリット・デメリットについて
メリット
1.社会保険料を安くすることで、手元に資金を多く残すことができ、残った分を他の投資に回すことも可能。
2.毎月の給与の支払い、給与明細の発行が不要。事務負担が減る。
デメリット
1.役員の賞与は事前確定届出給与の届出書を税務署に毎年提出する必要があるため、事務負担が増える。社会保険の賞与の手続きも増える。
2.事前確定届出は向こう1年分の賞与額をあらかじめ届けるが、届出額と実際に支給した賞与の額が1円でも違った場合は、全額損金不算入となる。(1円も経費にならなくなる。)
3.役員の退職金算定の際に、支給額の基礎となる月額の給与が低いため、退職金を払うことによる節税メリットが少なくなる。
4.役員賞与を多額に設定しすぎて資金繰りが悪化。賞与を支払う際の源泉所得税も多額になるため、資金繰りが苦しくなる可能性がある。
5.払う社会保険料額(厚生年金保険)が下がるということは、将来国から貰える年金も減る。
役員給与・賞与の注意点
役員に対して給料を支払う場合、通常は毎月定額を支給する定期同額給与が基本です。
なぜ定期同額なのかというと、役員の給料は毎月定額でないと、その定額を超えた部分は損金にできないからです。
役員の給料は定時株主総会などで決定しますが、今期は月額50万円で決定したとします。
年度の途中で利益が多く出そうだ!と思った時に、途中で「月額100万円の支給に変えて経費を増やし、法人税を節税しよう!」ということはまかり通りません。
基本的には役員の改定が認められるのは、原則年に一回だけです。(決算後3ヶ月以内)
税務署としては、利益操作をして税金を少なくさせないようになっているんですね。
賞与についても同じように、利益操作をさせないように、支給予定額ををあらかじめ税務署に届けさせる事前確定届出給与の届け出が必要になります。
最後に(個人的な見解)
今回は賞与を使った社会保険の節税について解説しました。
役員報酬が高額になり、社会保険料の負担が大きいなと感じた際に、役員賞与にして、社会保険料の負担を減らすというスキームでしたが、個人的には有効だと思います。
上記で掲げたデメリットあるので注意が必要ですが、将来年金がもらえるかどうかわからない状況で、自分の力で資産運用をしていきたいという方はオススメかと思います。
今回の話は以上です。
最後まで読んでいただきありがとうございました。
社会保険の具体的な計算結果については一切責任は持てませんので、ご自身の計算をする際は、社会保険労務士など専門家にご相談するなど自己責任でお願いいたします。
役員賞与を損金に算入するための手続き「事前確定届出給与」に関しては、別の記事でもっと詳しく解説しています。興味のある方はどうぞ!⇒役員賞与を経費に落とすには?事前確定届出給与の届出が必要 – 筒井一成税理士事務所 (tsutsui-office.net)
税理士/元資格の大原法人税法非常勤講師(2019年~2024年の5年間)
1982年生まれ
平成31年3月 税理士登録
2021年3月に独立 筒井一成税理士事務所を川崎市宮前区にて開業
2024年3月 事務所を世田谷区等々力に移転
現在世田谷区等々力を拠点として活動中。主に法人の顧問や相続のご相談をお受けしています。
ブログでは役に立つ税金の情報などを中心に発信していきます。
詳しいプロフィールはこちら
免責事項
本サイトのブログ内容は、投稿時点での税法その他の法令に基づき記載しています。
掲載記事に関する情報により被ったいかなる損害に関して、弊所は一切の責任を負わないものとします。
本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家にご相談の上行ってください。